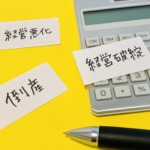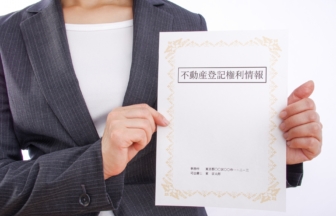不動産仲介業の倒産が過去最多!廃業率や倒産の理由とは?
最新の記事
軽量鉄骨と重量鉄骨の違いとは?特徴や耐用年数を説明します。
2023.12.06 / 最終更新日:2023.12.06

建築物を建てる場合、様々な構造がありますが、その中で「軽量鉄骨」と「重量鉄骨」というものがあります。この2つの鉄骨は、建物の種類や目的に応じて使い分けられ、それによって建物の強度なども異なってきます。
私たちの身近にも、軽量鉄骨や重量鉄骨で作られた建物は多く存在していますが、この2つの構造の違いは、具体的に分からないという人も多いと思います。そこで今回は、軽量鉄骨と重量鉄骨の違いとは?というテーマで、特徴や耐用年数について詳しく解説していきたいと思います。
軽量鉄骨の特徴
それではまず、軽量鉄骨とはどのようなものなのか、その特徴を解説していきましょう。軽量鉄骨とは、厚さが6mm未満の鋼材でアパートや戸建ての住宅など比較的小規模な建物の建築で用いられるものです。基本的に、2~3階建ての建物に多く採用され、鉄骨系のプレハブ住宅でもよく使われます。
重量鉄骨の特徴
次に、重量鉄骨とはどのようなものなのか、その特徴を解説していきます。重量鉄骨とは、厚さが6mm以上の鋼材で強度が重要になる高層ビルや大規模なマンション、大型商業施設や工場などを建てる際に用いられます。軽量鉄骨よりも強度が優れているため、より頑丈さが求められる建築物に対して採用される事が多いものになります。
軽量鉄骨と重量鉄骨それぞれのメリット・デメリット
では次に、軽量鉄骨と重量鉄骨それぞれのメリット・デメリットをご紹介していきましょう。
軽量鉄骨
軽量鉄骨の大きなメリットとしては、品質が安定しているという事が挙げられます。軽量鉄骨は、使用する前に事前に工場で規格化された部材を使用しているため、職人の経験年数などに左右される事無く品質が安定しているのです。
規格化されている事によって、工期も短くなるケースが多いのもメリットと言えます。また、耐震性・耐久性に優れている事もメリットとして挙げられます。
軽量鉄骨は、木造などに比べると耐震性が高く、倒壊の危険性は低く、適切なメンテナンスを行えば法定耐用年数よりも長く住み続けられるという特徴もあります。
一方、軽量鉄骨のデメリットとしては、防音性が低い事が挙げられます。軽量鉄骨は、防音性が木造住宅と同じ程度と言われており、アパートなどでは生活音が隣の家に漏れてしまうケースもあります。また、断熱性が低くリフォームがしにくいというデメリットもあります。
軽量鉄骨は、最初から規格化されたものを工場で組み立てて建築していくので、完成した後に間取りの変更がしにくく、ある程度リフォームに制約が出てしまうのです。そして断熱性が低いため、夏は暑く冬は寒くなりやすいのもデメリットと言えるでしょう。
重量鉄骨
重量鉄骨の最大のメリットとしては、強度が強いという事が挙げられます。柱や梁が厚く強度があり、少ない本数で作るので非常に丈夫で安定感があるのです。
設計の自由度があるため、理想的な間取りや空間を実現できるというメリットもあります。筋交いのない「ラーメン構造」では、開放的な吹き抜けなどの大きな空間を自由に作り出す事が出来ます。
軽量鉄骨とは異なり、リフォームの幅も広がり模様替えを簡単に行う事が出来るのです。鉄骨自体の厚みがある分防音性が高く、生活音などが聞こえにくいというメリットもあります。
一方、重量鉄骨のデメリットとしては、建築費用が高くなるという事が挙げられます。軽量鉄骨に比べて、骨組みの重さによって地盤をしっかり安定させる必要があり、土台部分の工事費用がかかります。また、鉄骨自体の厚みが増すだけ材料費用も高くなりがちです。
軽量鉄骨と重量鉄骨の耐用年数の違い
それでは最後に、軽量鉄骨と重量鉄骨の耐用年数の違いについて解説していきたいと思います。耐用年数とは、建築物の法的な耐久性を示すもので、確定申告をする際に計算する減価償却費の指標になる大切なものです。
耐用年数を超えてしまうと、法的にはその建物の価値はなくなると言われています。国税庁が示している、鉄骨構造の耐用年数は、下記のようになっています。
・3mm以下の鉄骨造:耐用年数19年
・3mm超4mm以下の鉄骨造:耐用年数27年
・4mm超の鉄骨造:耐用年数34年
上記のように定められており、厚さが6mm未満の軽量鉄骨は上記のいずれかに該当する事になります。一方、厚さが6mm以上の重量鉄骨は、4mm超の34年に該当する事になります。
まとめ
さて今回は、軽量鉄骨と重量鉄骨の違いとは?というテーマで、特徴や耐用年数について詳しく解説してみました。鉄骨の厚みによって、建てられる建築物の種類が変わり、耐用年数も異なります。
また、それぞれに特徴があるためメリット・デメリットがあり、その両方を用途によってうまく使い分ける事で、丈夫で長持ちする建築物を建てる事が出来るのです。
徳島で不動産のご相談ならアイケア不動産まで
不動産の売買・賃貸・管理・リフォームまで、経験豊富なスタッフが丁寧に対応させて頂きます。お気軽にご相談くださいませ。 TEL:088-660-6688 / Mail:info@aicare-fudosan.com